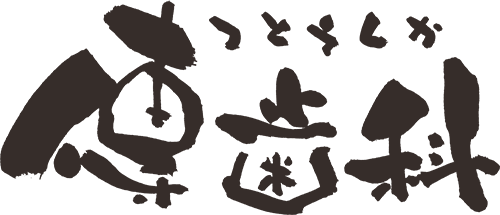
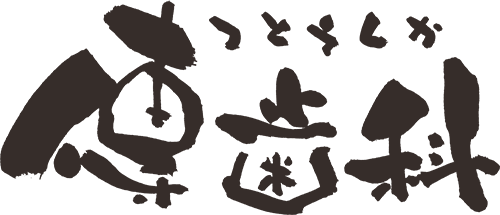

私の履歴書
(日経新聞 5月、30回連載より抜粋)初高座、さっぱりうけず
寄席への初出演は1967年5月6日、道頓堀にあった角座だ。出し物は「煮売屋」で駆け出しの落語家にふさわしい作品だったが、さっぱりうけずに客席は静まりかえっていた。
歌え!MBSヤングタウンくすぶっていた内弟子時代、飛躍のチャンスはひょんなところから訪れた。
毎日放送が深夜ラジオ番組で新機軸を打ち出す、司会者を助けて会場を盛り上げる若手芸人を探しているというのだ。師匠の桂小文枝は、本業の落語からはみだすところがあっても、声を掛けられた仕事は原則断らない主義だった。まだ海のものとも山のものともつかない私をオーディションに送り出してくれた。
みな昔ながらの小咄を繰り出したが、私は自作のネタで勝敗した。
会場を埋めるのは高校生中心で、若者が何を面白がり、どこをくすぐれば共感してくれるのか勘所には自信があった。落語臭に染まりきってない若手芸人像にピタリとはまったようだった。
草創期は若者が会場になかなか集まらなかったので策を練り、リクエストはがきには直筆の礼状を書いたり、ギャグも必死でねり出した。
ひとりぼっちでいるときのあなたにロマンチックな明かりをともす、便所場の電球みたいな桂三枝です。
このキャッチフレーズは深夜放送の聞き手に届くように考案した。折りしも段階の世代が受験期に入っていた。孤独な受験戦争を闘う若者同士、本番や悩みを共有し合おう、というメッセージだ。
半年ほどたつと「ヤングタウン」は押しも押されもせぬ人気番組に成長した。
深夜放送の仕事が立て込み、落語家の弟子業務に手が回らなくなりだした頃、「吉本興業の専属にならへんか、弟子のままやったら仕事できへんやろ。独り立ちできるよう、師匠に話つけたろ」と中邨秀雄(後に吉本社長)さんから誘いをうけ、桂三枝は吉本専属の落語家になる。そして、放送関係の仕事が続々と舞い込んだ。
二足のわらじろくに下積みさえ経てこなかった若者が、並み居る先達を抑えて座るには居心地がよくない。東京の落語界なら芸歴と技能に見合った序列があるが、関西ではお客様を呼べる力があるか否かが尺度である。
話の枕まではいいのだが、本題に入った途端、昔ながらの世界にすんなり入れない。普段のお客様の前でしゃべっている口調と古典に求められるものが違うからだ。この違和感が拭えず苦しんだ。
自分がやると江戸の昔にすんなり入っていけない。
普段のテレビ口調との落差が大きすぎ、自分が冷めてしまうのだ。
自分なりのオリジナルな笑いを追及できないかと苦しんでいた、ある日、桂文紅さんの新作落語「テレビ葬式」を聞いてこれだと直感。自分に向いているのは現代性のある落語かもしれない、東京では三遊亭円丈さんが「グリコ少年」という新作落語で話題をさらっており、しゃべりが決して落語口調でないことに意を強くした。
作法に縛られずともいいではないか。無限の前途が広がったように思えた。腹をくくって1983年、古典に終止符を打つことにした。




| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15:00 - 19:00 | ● | ● | ● | ● | ▲ |