ツトウ歯科の特徴
特徴1
0歳からの歯医者さんご存知ですか?お口(顎)育て、むし歯予防、将来の綺麗な歯並びのために、0歳から出来ることがあります。当院は、食育アドバイザーの資格を持つスタッフが在籍しており、「 お子様の食生活の教室」も行っております。お気軽にご相談ください。特徴2
女性歯科医師が担当の小児歯科当院では、火曜日の午後に女性の先生に来て頂いています。お子様も安心して治療を受けていただけます。特徴3
しっかりした説明、丁寧な痛みの少ない治療口腔内カメラやオリジナルの資料を用いて、わかりやすく説明させて頂きます。出来るだけ痛みの少ない治療を心がけ、歯の寿命を考えた健康なお口を目指しています。歯は健康の源、食を含めた全身の管理や予防歯科にも力を入れています。特徴4
徹底した感染予防オートクレーブ滅菌システムを用いて、歯を削るタービン等も1本ずつ滅菌し清潔に保っております。その他、感染予防に配慮し徹底した衛生管理を行っております。特徴5
日・祝日以外は診療を行っております基本的に予約制になっておりますが、痛みがある等症状がある場合は随時ご連絡ください。特徴6
訪問歯科診療(往診)お体が不自由な方、入院中など歯科医院への通院困難な方に、訪問歯科診療(往診)を行っております。世間では訪問歯科診療が知られていなかった平成8年から行っておりノウハウは熟知しております。医療保険や介護保険での診療が可能なので、ご安心ください。訪問歯科診療には適応がございますので、一度ご相談ください。
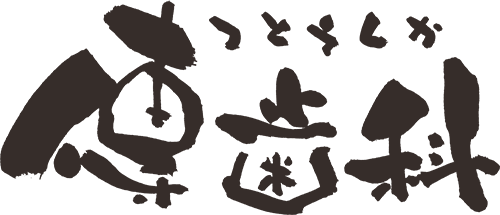
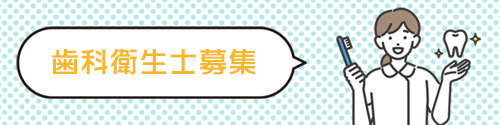
 高砂市の歯科医院「ツトウ歯科医院」は、高砂市と加古川市の境に位置し、宝殿中学校の隣にあります。1988年に開業して以来、地域の皆様に通って頂きやすい「歯を大切にする歯科医院」を目指してきました。今後も、お子様からおじいちゃん・おばあちゃんまで、どの世代の患者様にもご家族様で安心して通って頂ける地域に密着した歯科医院でありたいと願っております。
高砂市の歯科医院「ツトウ歯科医院」は、高砂市と加古川市の境に位置し、宝殿中学校の隣にあります。1988年に開業して以来、地域の皆様に通って頂きやすい「歯を大切にする歯科医院」を目指してきました。今後も、お子様からおじいちゃん・おばあちゃんまで、どの世代の患者様にもご家族様で安心して通って頂ける地域に密着した歯科医院でありたいと願っております。